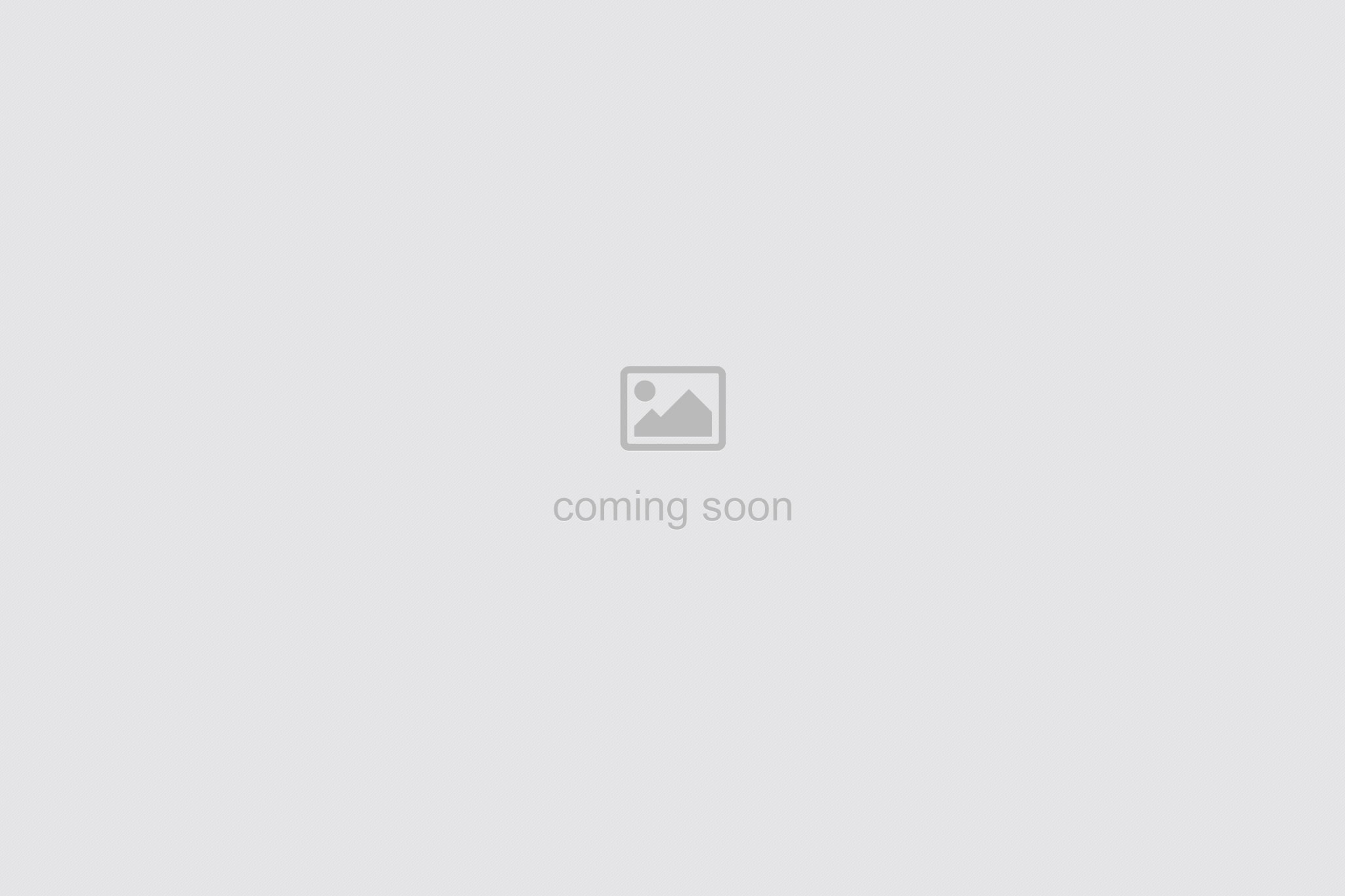ブログ
先生たちもがんばります!!
2021-02-03
朝8時前の校長室。まだのぼりたての朝日がまぶしいです。校長室に先生方が続々と集まってきました。どんなふうに授業をすすめるのが良いか真剣な話し合いが始まりました。先生たちもがんばります。
くま先生日記☆No.82 「立春―3年生は中学校最後のテスト―」
2021-02-03
こんにちは!
昨日は節分。
そして、今日は「立春」。暦(こよみ)の上では、今日以降は春 となります。
となります。
まだまだ寒くて、なかなか春とは実感できませんが…。
そして、3年生は今日から三日間、中学校生活最後の「学年末テスト」ですね
今は葉もなく枯れ木のようにみえる桜の木のつぼみも、よく見ると春に向けてつぼみがふくらみ、開花を待っての準備中
3年生のみなさんも勉強にいそがしかったり、気分的にもどんよりして、今は心は冬かもしれませんが、桜と同じく、新しい春に着実に向かっているのです
がんばってくださいね
くま先生日記☆No.81 節分
2021-02-02
今日は1897年以来、124年ぶりに2月2日が節分の日になりました。
節分といえば、「鬼は外、福は内」恵方巻き・いわし(鰯)・豆まき・鬼ですね
ところで、みなさんは節分の日にどうして「いわし(鰯)」を食べるのか知ってますか?
いわしは、DHA・カルシウムなどを豊富に含む栄養価が高い魚です。
ですが、陸にあげるとすぐに弱ってしまうことや、貴族が食べるものではない卑しい魚であるということから、「弱し(よわし)」や「卑し(いやし)」が語源といわれています。
さらにいわしはにおいが強い魚であることから、弱く、卑しく、においの強いいわしを食べると、体内の「陰の気を消す」という意味をもっていたようです。
ですが、陸にあげるとすぐに弱ってしまうことや、貴族が食べるものではない卑しい魚であるということから、「弱し(よわし)」や「卑し(いやし)」が語源といわれています。
さらにいわしはにおいが強い魚であることから、弱く、卑しく、においの強いいわしを食べると、体内の「陰の気を消す」という意味をもっていたようです。
また、いわしは『魔除け』のための飾りとしても。
これは、「柊鰯(ひいらぎいわし)」「節分鰯」、西日本では、「焼嗅(やいかがし)」とも呼ばれます。
もともと日本では、形の見えない災害、病、飢饉などの人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業と考えられおり、鬼は邪気や厄の象徴とされてきました。
鬼はいわしのにおいや焼いた時に出る煙、とがったものが大嫌いなため、いわしの頭を柊に刺して戸口などに下げておき、『魔除け』としていたようです。
これは、「柊鰯(ひいらぎいわし)」「節分鰯」、西日本では、「焼嗅(やいかがし)」とも呼ばれます。
もともと日本では、形の見えない災害、病、飢饉などの人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業と考えられおり、鬼は邪気や厄の象徴とされてきました。
鬼はいわしのにおいや焼いた時に出る煙、とがったものが大嫌いなため、いわしの頭を柊に刺して戸口などに下げておき、『魔除け』としていたようです。
旧暦が使われていた頃の立春の日というのは新しい年の始まりの日で、その前日の節分の日は大晦日にあたります。
その大晦日に、新年に向けての無病息災の儀式のアイテムとして、いわしに関することが定着したと考えられています。
ただ、節分にいわしを食べる風習があるのは、関西地区などの西日本が中心とのことです。
今年の方角は、南南東、南南東です。 (鬼滅の刃ふう言うてみました。笑)
(鬼滅の刃ふう言うてみました。笑)
くま先生日記☆No.81 節分
2021-02-02
今日は1897年以来、124年ぶりに2月2日が節分の日になりました。
節分といえば、「鬼は外、福は内」恵方巻き・いわし(鰯)・豆まき・鬼ですね
ところで、みなさんは節分の日にどうして「いわし(鰯)」を食べるのか知ってますか?
いわしは、DHA・カルシウムなどを豊富に含む栄養価が高い魚です。
ですが、陸にあげるとすぐに弱ってしまうことや、貴族が食べるものではない卑しい魚であるということから、「弱し(よわし)」や「卑し(いやし)」が語源といわれています。
さらにいわしはにおいが強い魚であることから、弱く、卑しく、においの強いいわしを食べると、体内の「陰の気を消す」という意味をもっていたようです。
ですが、陸にあげるとすぐに弱ってしまうことや、貴族が食べるものではない卑しい魚であるということから、「弱し(よわし)」や「卑し(いやし)」が語源といわれています。
さらにいわしはにおいが強い魚であることから、弱く、卑しく、においの強いいわしを食べると、体内の「陰の気を消す」という意味をもっていたようです。
また、いわしは『魔除け』のための飾りとしても。
これは、「柊鰯(ひいらぎいわし)」「節分鰯」、西日本では、「焼嗅(やいかがし)」とも呼ばれます。
もともと日本では、形の見えない災害、病、飢饉などの人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業と考えられおり、鬼は邪気や厄の象徴とされてきました。
鬼はいわしのにおいや焼いた時に出る煙、とがったものが大嫌いなため、いわしの頭を柊に刺して戸口などに下げておき、『魔除け』としていたようです。
これは、「柊鰯(ひいらぎいわし)」「節分鰯」、西日本では、「焼嗅(やいかがし)」とも呼ばれます。
もともと日本では、形の見えない災害、病、飢饉などの人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業と考えられおり、鬼は邪気や厄の象徴とされてきました。
鬼はいわしのにおいや焼いた時に出る煙、とがったものが大嫌いなため、いわしの頭を柊に刺して戸口などに下げておき、『魔除け』としていたようです。
旧暦が使われていた頃の立春の日というのは新しい年の始まりの日で、その前日の節分の日は大晦日にあたります。
その大晦日に、新年に向けての無病息災の儀式のアイテムとして、いわしに関することが定着したと考えられています。
ただ、節分にいわしを食べる風習があるのは、関西地区などの西日本が中心とのことです。
今年の方角は、南南東、南南東です。 (鬼滅の刃ふう言うてみました。笑)
(鬼滅の刃ふう言うてみました。笑)
くま先生日記☆No.81 節分
2021-02-02
今日は1897年以来、124年ぶりに2月2日が節分の日になりました。
節分といえば、「鬼は外、福は内」恵方巻き・いわし(鰯)・豆まき・鬼ですね
ところで、みなさんは節分の日にどうして「いわし(鰯)」を食べるのか知ってますか?
いわしは、DHA・カルシウムなどを豊富に含む栄養価が高い魚です。
ですが、陸にあげるとすぐに弱ってしまうことや、貴族が食べるものではない卑しい魚であるということから、「弱し(よわし)」や「卑し(いやし)」が語源といわれています。
さらにいわしはにおいが強い魚であることから、弱く、卑しく、においの強いいわしを食べると、体内の「陰の気を消す」という意味をもっていたようです。
ですが、陸にあげるとすぐに弱ってしまうことや、貴族が食べるものではない卑しい魚であるということから、「弱し(よわし)」や「卑し(いやし)」が語源といわれています。
さらにいわしはにおいが強い魚であることから、弱く、卑しく、においの強いいわしを食べると、体内の「陰の気を消す」という意味をもっていたようです。
また、いわしは『魔除け』のための飾りとしても。
これは、「柊鰯(ひいらぎいわし)」「節分鰯」、西日本では、「焼嗅(やいかがし)」とも呼ばれます。
もともと日本では、形の見えない災害、病、飢饉などの人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業と考えられおり、鬼は邪気や厄の象徴とされてきました。
鬼はいわしのにおいや焼いた時に出る煙、とがったものが大嫌いなため、いわしの頭を柊に刺して戸口などに下げておき、『魔除け』としていたようです。
これは、「柊鰯(ひいらぎいわし)」「節分鰯」、西日本では、「焼嗅(やいかがし)」とも呼ばれます。
もともと日本では、形の見えない災害、病、飢饉などの人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業と考えられおり、鬼は邪気や厄の象徴とされてきました。
鬼はいわしのにおいや焼いた時に出る煙、とがったものが大嫌いなため、いわしの頭を柊に刺して戸口などに下げておき、『魔除け』としていたようです。
旧暦が使われていた頃の立春の日というのは新しい年の始まりの日で、その前日の節分の日は大晦日にあたります。
その大晦日に、新年に向けての無病息災の儀式のアイテムとして、いわしに関することが定着したと考えられています。
ただ、節分にいわしを食べる風習があるのは、関西地区などの西日本が中心とのことです。
今年の方角は、南南東、南南東です。 (鬼滅の刃ふう言うてみました。笑)
(鬼滅の刃ふう言うてみました。笑)